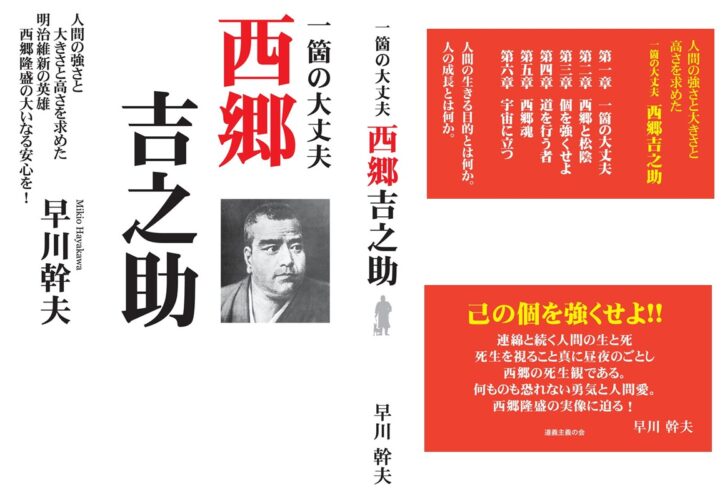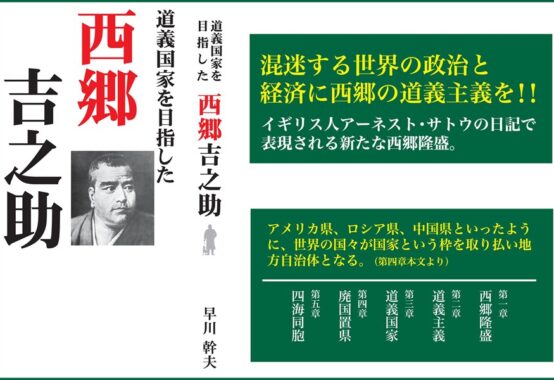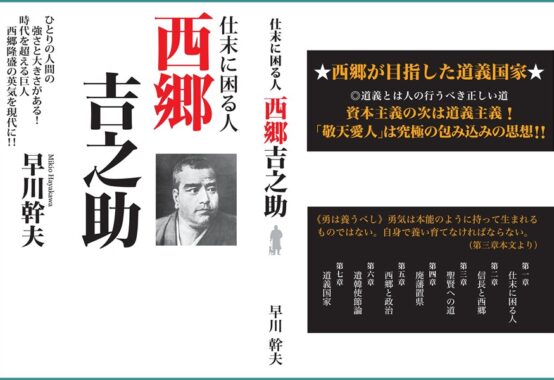純正の強さ
西郷と松陰に共通するのは二人とも純正の強さを持っていたことである。特に松陰は純正であることが大切と考えた。「至誠にして動かざるものは、未だ之れ有らざるなり」。この文は、松陰の遺書ともいえる『留魂録』第一章に出てくる。もともと孟子の言葉であるが、松陰は文字どおりこの至誠をもって高杉晋作や久坂玄瑞ら松下村塾生を動かし、それによって長州藩を討幕藩に転じさせ、ついには江戸幕府を倒すまでに至った。松陰は江戸天馬町の獄舎で『留魂録』を二日で書きあげ、翌日の一八五九年(安政六年)十月二十七日には処刑される。松陰三十歳である。
『留魂録』の表紙は松陰の特徴ある右肩あがりの文字で「留魂録」と標題があり、その横に有名「身はたとひ武蔵の野辺に朽ぬとも留置まし大和魂」の歌が書かれている。その横には「十月念五日」(念五日=二十五日)と日付が記され、その下には松陰が好んだ号「二十一回猛士」とのみ書かれている。二十一回猛士の文字がなんとも誇らしげに松陰の意気を表している。
松陰は混じり気のないことを純金にたとえている。至誠も純金でなければならない。それを金の量ではなく、小量であっても純金であることが大切としている。たとえ微量であってもほかの物質が入ったら純金でなくなる。至誠は一切の我欲をなくし純正の志でなければならない。そうであってこそ価値があり、時代を貫く強さと、時代を超えた輝きを放つのである。
一八五三年(嘉永六年)、ペリーの浦賀来航を機に日本は欧米列強の外圧を受け、好むと好まざるにかかわらず歴史的な大変革を断行しなければならなかった。この国難にあたり、なんとか日本を救いたいという強い思いが、松陰に「今為すべきものは、至誠をもって為す」という行動を取らせた。これが脱藩でありアメリカへの密航であり、野山獄内での教室であり松下村塾である。
地位や権力を得てから、組織を十分に構築して後になど全く考えなかった。長州藩士であろうと、脱藩浪人であろうと、獄につながれていようと、「今為すべきものは、至誠をもって為す」ことが、一番スピードがあって効率・効果があると思っていたのであろうか。松陰の行動考えを見ているとそのように思えてくる。日本の国難に「生死を度外に置き至誠をもって行動する」。この松陰の思いが、自らの死によって高杉や久坂たち塾生に火をつけ、その火が藩をゆり動かし突き動かし引きずり回したのである。火のついた塾生の若者たちが藩政を動かし、二千余りの兵を率いて京都に出兵するという暴挙に駆り立てた。さらに、第一次・第二次の長州征伐で幕府と戦争状態となり、長州三十二万石が一挙に過激な藩と化すまでになった。まさしく「至誠にして動かざるものは未だ之れ有らざるなり」の証明であるといえる。
西郷も『遺訓』の中で「誠」「至誠」の重要さを説いている。「至誠」は現代の日本では死語となっている言葉であろう。しかしながら、この言葉は本来、松陰が言うように純金の値があり、純正の強さを持ち人の道に沿い、本当の意味で人間としての強さを与える。
次の文章は、『遺訓』七項にある西郷の言葉である。
「事大小と無く正道を踏み至誠を推し一事の詐謀を用ふ可からず。人多くは事の指支ふる時に臨み、作略を用ひて一旦其の指支を通せば、跡は時じ 宜ぎ次第工夫の出来る様に思へ共、作略の煩ひ屹度と生じ、事必ず敗るるものぞ。正道を以て之を行へば、目前には迂遠なる様なれとも、先きにいけば成功は早きもの也」
(どんな大きい事でもまたどんな小さい事でも、いつも正しい道をふみ、真心をつくし、決していつわりのはかりごとを用いてはならない。人は多くの場合、ある事にさしつかえができると何か計略を使って一度そのさしつかえをおし通せば、あとは時に応じて何とかいいくふうができるかのように思うが、計略したための心配事がきっと出てきて、その事は必ず失敗するにきまっている。正しい道をふんで行うことは目の前では回り道をしているようであるが、先に行けばかえって成功は早いものである)