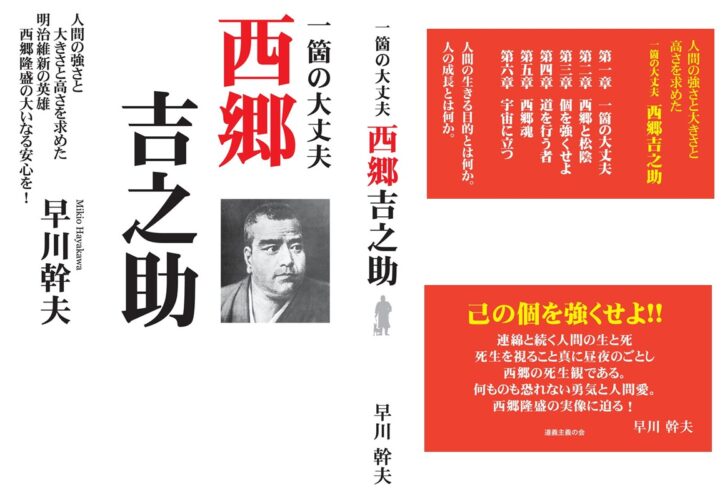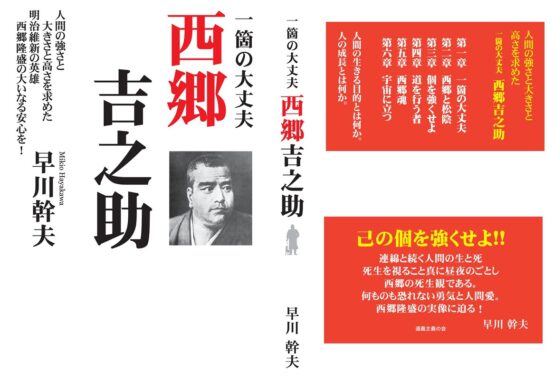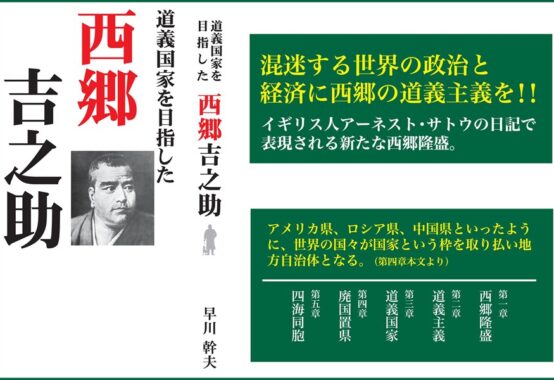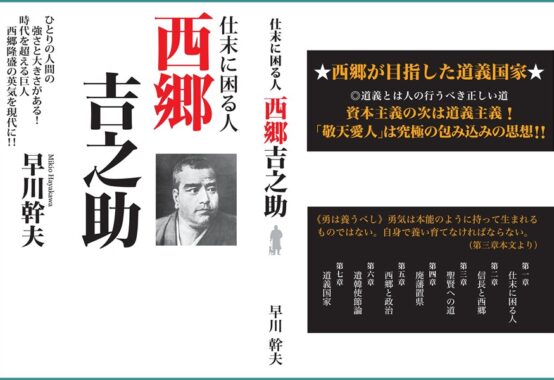勝海舟が評した西郷の大きさ
勝海舟の『氷川清話』に西郷を評した言葉がある。
「坂本龍馬が西郷におよぶことのできないのは、その大胆識と大誠意とにあるのだ。おれの一言を信じて、たった一人で、江戸城に乗り込む。おれだってことに処して、多少の権謀を用いないこともないが、ただこの西郷の至誠は、おれをしてあい欺くことができなかった。このときに際して、小しょうちゅう籌浅略を事とするのは、かえってこの人のためにはらわたを見すかされるばかりだと思って、おれも至誠をもってこれに応じたから、江戸城受け渡しも、あのとおり立たちばなし談の間にすんだのさ」
品川での談判のとき「当時のおれは、羽織袴で馬に乗り、従者一人つれたばかりで、薩摩屋敷へでかけた。まず一室へ案内せられて、しばらく待っていると、西郷は庭の方から、古洋服に薩摩風の引っ切り下駄をはいて、例の熊次郎という忠僕を従え、平気な顔で出てきて、『これは実に遅刻しまして失礼』と挨拶しながら座敷にとおった。
そのようすは、少しも一大事を前に控えたものとは思われなかった。さて、いよいよ談判になると、西郷は、おれのいうことを一々信用してくれ、その間一点の疑念もはさまなかった。
『いろいろむつかしい議論もありましょうが、私が一身にかけてお引き受けします』。
西郷のこの一言で、江戸百万の生霊[人間]も、その生命と財産とを保つことができ、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。
もしこれが他人であったら、いやあなたのいうことは自家撞着だとか、言行不一致だとか、たくさんの兇徒があのとおり処々に屯集しているのに、恭順の実はどこにあるかとか、いろいろうるさく責めたてるに違いない。
万一そうなると、談判はたちまち破裂だ。しかし西郷はそんな野暮はいわない。その大局を達観して、しかも果断に富んでいたには、おれも感心した。このときの談判がまだ始まらない前から、桐野利秋などいう豪傑連中が、多勢で次の間へきて、ひそかにようすをうかがっている。薩摩屋敷の近傍へは、官軍の兵隊がひしひしと詰めかけている。
そのありさまは実に殺気陰々として、ものすごいほどだった。しかるに西郷は泰然として、あたりの光景も眼にはいらないもののように談判をしおえてから、おれを門の外まで見送った。
このとき、おれがことに感心したのは、西郷がおれに対して、幕府の重臣たるだけの敬礼を失わず、談判のときにも、終始坐を正して手を膝の上にのせ、少しも戦勝の威光でもって敗軍の将を軽べつするというようなふうがみえなかったことだ。その胆量の大きいことは、いわゆる天空海闊で、見識ぶるなどということは、もとより少しもなかった。
これは西郷の偉さを評価することで、その実、海舟自身の偉さをアピールしているように見えなくもないが、何分勝海舟は薩長同盟の立役者である坂本龍馬の師。
幕府の最後を取り仕切ったのも海舟である。名人は名人を知るともいう。それなりの西郷評とみてよい。
この海舟の話を聞いていると西郷という人間が少し見えてくる。このときの西郷の海舟への接し方がそのまま、※戊辰戦争における東北戦争での庄内藩(山形県・鶴岡市)藩主酒井忠篤への接し方であった。
降伏した年若い藩主(十六歳)に対して、海舟同様に戦勝の威光で敗軍の将扱いをすることなく、相手の置かれた立場を思いやった心ある対応をした。西郷の側にいた薩摩藩士・高島鞆之助(のち陸軍中将・陸軍大臣)は「余りに御謙譲に過ぎてどちらが降伏するのか分からん」と嘆じたという。西郷のこの行為が、藩主以下庄内藩士を感動させ、明治になって藩主酒井忠篤、家老菅実秀ほか十数名の藩士が西郷の教えを請おうと鹿児島に留学するきっかけとなったのである。
またこのきっかけがあればこそ『西郷南洲遺訓』が現存し、今日もなお出版され多くの人に読まれているといえる。
『遺訓』は旧庄内藩の関係者が西郷から聞いた話をまとめたものである。そうでなければ、己の考えや教えを後世に残すなどという未練がましいことを西郷がするはずもない。
『遺訓』は現存せず西郷像はますます分かりにくいものとなっていたであろう。当時、西郷を知る者と言われていた海舟にしても「西郷は実に漠然たる男だった」と述べている。海舟をしても西郷の全体は見えなかったのである。
倒幕までの西郷は歴史家も評価しているが、明治になってからの西郷は行動目的が見えないと評価されていない。その理由はどこにあるのであろうか。
維新後の西郷は鬱の状態にあったと歴史家や作家諸氏に思わせてしまっている。倒幕を果たしたことで敬愛する斉彬の恩にも報いることができ、己の役目も終わったと思った。
また、西郷の持つ古風な考え、理想主義的なもの、情を重んじる体質が明治という新時代に向かず、政府内でも受け入れられなかった。さらに、死に対する願望が西郷の特質であり、厭世や隠棲といった行動として表れるとされた。
維新後の西郷をどの歴史家も大体このようにとらえている。そして現在に至ってもなおこの範囲から出ることはなく定説となっている。
しかしながら、『遺訓』に表れている「西郷」を見ると、どうしてもそのようには思えないのである。西郷の人間としての志は高く孔子・孟子レベルを目指している。
政治においても、あるべき治世の形をはっきりと持っており、そこに至るための段階も考え尽くすことができ、またこれを実行に移し得る力量も併せ持っている。これが『遺訓』の中に表れている西郷像といえる。西郷の本質は革命家であり改革者である。
この本質があるからこそ私学校があり、西南戦争がある。学者や評論家にはなり得ず、また保守政治家や権威主義の官僚であってはならないと思っている。
西郷の気性からしても第二第三の維新を起こすべきであると考えもしたであろうが、弱小国日本が兵力・科学技術・産業において格段の開きがある大国欧米列強の監視の中で明治維新を断行しなければならなかった。すでに日本は彼らの武力に屈し、幕末に和親条約や修好通商条約といった不平等条約を締結させられている。
このような中で旧体制を打ち倒し新政府を樹立するには、細心にして慎重を期し、彼らにつけ入るすきは、絶対に与えてはならない。内政干渉する間も与えず素早く成し遂げなければならないのである。この点に絞って西郷は倒幕を進めている。江戸城の総攻撃を中止し海舟との会談で江戸城無血開城に至ったのも、根底には西郷のこの考えがある。
上野の彰義隊攻撃のとき指揮権をめぐって、長州藩の大村益次郎と薩摩藩の海江田信義(有村俊斉)が争った。こんな小さなことで主導権争いをしている暇はないと、威勢の良さと勢いだけが取りえの参謀・海江田信義を西郷は抑えて、大村に指揮権を渡し自らは薩摩軍を率いて最も激戦が予想される黒門口の攻撃に当たるのである。
倒幕という国内戦を三年も五年も引きずっていたら、幕府側も官軍側も疲弊し、日本の国力は衰えてしまう。それこそ清国やインドや他のアジア諸国のように欧米列強の餌食にされていただろう。現にアジア諸国が欧米の植民地から独立するのは二十世紀の半ばになってからである。
西郷は維新後もこの姿勢を貫いていた。新国家を成立させたからといって有頂天になってはおれないのである。まだまだ日本の国力は弱く、国民は政権の移行で動揺している。誕生したばかりの新国家で絶対に避けなければならないのは、政府内の権力闘争である。政府内の内紛となり内乱内戦にも発展しかねない。
明治新政府は薩・長・土・肥の寄り合い所帯であり、倒幕の段階から新政権内での勢力争いを演じていた。
一八七一年(明治四年)七月の廃藩置県まで、新政府は国軍も徴税権も持たない全く脆弱な基盤の上にあった。このような状況の中で西郷が政権にとどまれば、西郷が好むと好まざるにかかわらず、西郷党と大久保党が政権内にできてしまう。
最大勢力薩摩が二つに割れ、そこに長州や土佐、肥前の勢力、果ては朝廷までもが巻き込まれた政争となりかねない。成立間もない新政府内で内紛を起こしてはならない。外国にあなどられ内政干渉の口実となる。
薩摩藩において藩主の座をめぐり、斉彬派と久光派が抗争し悲惨な結果を招いたことを西郷は近くで見ている。
中国の歴代王朝にしても内紛による亡国の例はいくらでもある。欧米列強が虎視眈々と日本をすきあらばと狙っているとき、万国と対峙することとなった新生明治国家で、権力闘争による内紛や内乱など決して起こしてはならない。
仮にその芽が己にあるとするなら、自身が政権から離れるべきであると思った。西郷は戊辰戦争の大勢が決すると朝廷に願い出て鹿児島に帰った。郷里にあっても己に権力が集まらないよう配慮し、もっぱら山野に分け入って狩りや温泉に浸り世俗から離れていた。
しかし、一八七〇年(明治三年)十二月、政府は廃藩置県の必要に迫られ、岩倉具視を勅使として鹿児島に下向させ、西郷に上京の勅命を伝える。
西郷は政府の政策すべてを一任するという条件で引き受けるのである。
廃藩置県は第二の維新といわれるほど新政府にとっては重大な局面であった。政権内を見渡してもこれを実行し得る役者はいない。長州の木戸は胆力不足で、第一貫禄がない。山県、伊藤、井上では実力不足で無理である。
大久保では薩摩軍が動かない。大久保が権力を握って四、五年すれば可能であろうが、それまでの時間はない。
また、大久保は当時薩摩藩の所有者であり旧主君であった久光の反対と反撃を受けてまで、さらに自身の地位を賭してまで断行するというリスクは負わない。大久保が木戸、山県、伊藤、井上ら長州勢と合体して未成熟のまま実行することはまずない。
それまでの大久保の経歴を見ても分かるように、組織の中で権力を得て組織体の特性を知り、非情ともいえる権限を行使する。それによって冷厳非情のカリスマ性を得ていく。しかし、これはあくまでも組織体の中でのことであって、その組織体が強大でなければその権力は小さいのである。
これらの諸々の条件を分析してみても、廃藩置県を断行し得るのは西郷以外に存在しない。久光の反抗と反撃をも恐れず、また沖永良部島から赦免されて帰るとき、まだ罪を許されていないのに独断で村田新八を連れ帰ったことや、江戸城総攻撃のとき西郷の一存で攻撃を中止させたことなど、己の責任において一命を賭して決断し行動できるという西郷の胆力が必要である。
それに、薩摩藩士に絶大な信頼と人望があり、若い兵士は久光の命には服さなくとも西郷のためであれば身命を賭して戦うという藩士が多いなど、西郷でなければ薩摩軍は動かせない。
明治政府が名実ともに国家となるためには廃藩置県という中央集権化は是非とも実現しなければならない仕組みであり、日本史上の大仕事であった。
誰がどのように考えてみても一八七一年(明治四年)のこの時期、この仕事を成し遂げられるのは日本に西郷だけであった。結局は郷里鹿児島で隠棲していた聖賢の道を行う者、一箇の大丈夫西郷吉之助に頼るほかなかったのである。
いったん引き受けると西郷の仕事は早い。この辺の呼吸は心得ている。直ちに上京し、政府に勅命で薩・長・土・肥の四藩に一万の兵を提供させる。自身は鹿児島に戻り自ら率先して薩摩軍を率いて再び上京する。
こうして集結した一万の兵を御親兵として東京に常駐させた。そして木戸、大久保、山県、井上らと会議を重ね、自身はこれを実行すべく政府代表として木戸とともに参議に就任。
一八七一年(明治四年)七月十五日、ついに廃藩置県が行われるのである。西郷が上京してからわずか四カ月であった。これにより明治政府が名実ともに国家としての体を成していくのである。
※戊辰戦争 明治維新期の内乱。一八六八年(慶応四年)一月から一八六九年(明治二年)六月までの約一年五カ月、近畿地方から蝦夷地に及ぶ東日本一帯で、新政府と旧徳川幕府・佐幕派諸勢力との間で戦われた。鳥羽・伏見の戦い、上野戦争、北越戦争、東北戦争、函館戦争(五稜郭の戦い)からなる。一八六八年一月三日、旧幕府軍と薩摩・長州軍との間に鳥羽・伏見の戦いが勃発、これに勝利した薩長軍は新政府軍として東海・東山・北陸の三道に分かれて江戸へ進撃、四月十一日江戸を無血占領し、五月十五日彰義隊との上野戦争に一日で勝利した。一方、北陸では長岡藩が抵抗して北越戦争が勃発、五月三日には東北の二十五藩が連合して奥羽列藩同盟が結成され、のち北越六藩が参加して奥羽越列藩同盟となり、東北戦争が勃発した。七月末には長岡・新潟の占領で北越戦争が終結し、九月二十二日会津落城で東北戦争も終結した。
(『角川新版・日本史辞典』〈角川書店〉から引用)