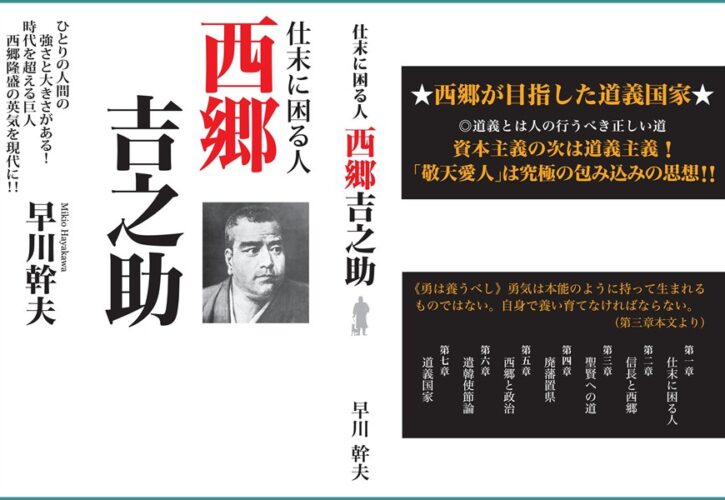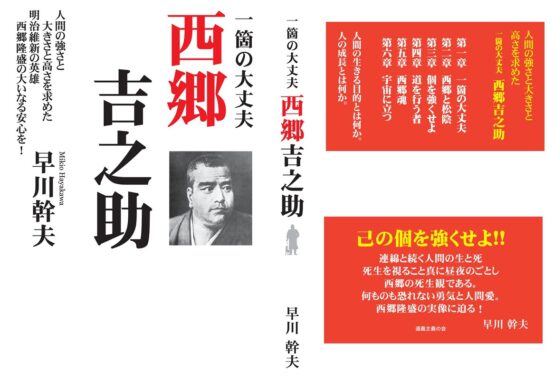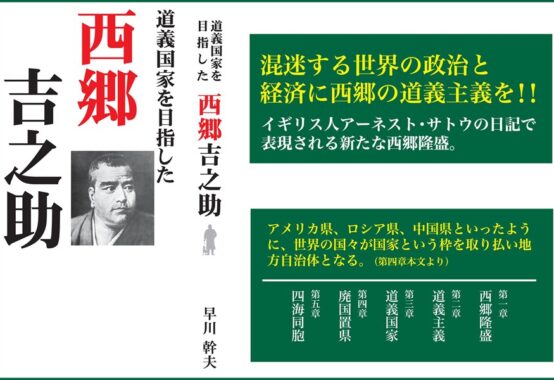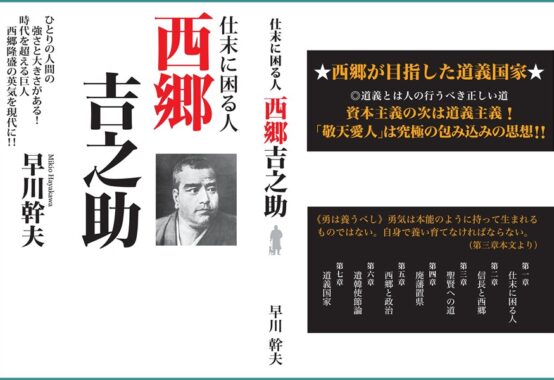第五章 西郷と政治
政治という行為
政治家は一般の人から「先生、先生」と呼ばれている。市町村議員よりは県議会議員の方が「偉い」とみなされ、県議会議員よりは国会議員が「偉い」とみなされている。人は「先生」と呼ばれると悪い気はしない。いつもそう呼ばれていると立派でなくとも、ついつい偉ぶってくる。
政治という行為は国民の主権を代行させてもらっているのであるから「議員」と呼ぶべきで「先生」とは言わない方がよい。「先生」といわれると、「俺はお前たちとは違うんだ」
というような妙な選民意識が出てこないともかぎらない。国民の主権をまかせてあげているのだから、任せている側が、任せられている側をきちっとその職務を行っているかどうか監視しなければならない。しかしながら、権限を与えているので、任せられている側が任せている側を動かしてしまう。そこに政治という行為の恐ろしさがある。現代は民主主義という、確かに理想に近い政治形態ではあるが、常に改善と修正を加えていかなければ、民主主義という専政・圧政が起こらないともかぎらない。
「万民の上に位する者、己れを慎み、品行を正しくし、嬌奢を戒め、節倹を勉め、謀りなば、維新の功業は遂げられ間敷也。今と成りては、戊辰の義戦も偏へに私を知 営みたる姿に成り行き、天下に対し戦死者に対して面目無きぞとて、興りに涙を催されける」『遺訓』四項)
(多くの国民の上に立つ者(施政の任にある者)は、いつも自分の心を慎み、身の行いを正しくし、おごりやぜいたくを戒め、無駄を省きつつましくすることに努め、仕事に励んで人々の手本となり、一般国民がその仕事ぶりや生活を気の毒に思うくらいにならなければ政府の命令は行われにくいものである。しかしながら今、維新創業のときというのに、家をぜいたくにし衣服をきらびやかに飾り、きれいな妾を囲い、自分一身の財産を蓄えることばかりをあれこれと思案するならば、維新のほんとうの成果を全うすることはできないであろう。今となっては戊辰の正義の戦いもひとえに私利私欲をこやす結果となり、国に対しまた戦死者に対して面目ないことだと言ってしきりに涙を流された)
政治という行為には権限が伴ってくる。それゆえどうしてもその行使された権限には国民は従わざるを得なくなる。
日本国憲法には、公務員は国民全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはならないと明記されている。しかしながら、大臣や官僚のトップである事務次官は、苦労してやっと手に入れた地位であるとの思いが強いので、全体の奉仕者という意識にはなりにくい。これ以外の公務員でも、勉強して試験に合格し自分の力でなったのであるから、業務の遂行と自ら属する組織の維持には忠実であっても、国民全体の奉仕者としての意識は薄い。
ほとんどすべての経費が税金でまかなわれ、支出するときの決済も数字の確認だけであるため、何億の金であろうと表示された「数字」という感覚になってしまう。民間の企業のような損益や経費意識がほとんどない。予算は要求するものであり、概算として多めに要求するのが常識となっている。しかも、獲得した予算は年間で使い切らなければならない。人の金(税金)だからいくら使っても自分のふところは痛まない。各省庁から地方の機関に至るまで概算で要求し、使うことばかりにエネルギーをかけ、節約をしようとせず、不足すれば増税で補おうなどと横着な考えを持っている。西郷に言わせれば、国民の血税を使うのであるから、政治家や公務員は「己れを慎み、品行を正しくし、矯奢を戒め、節倹を勉め、職事に勤労して国民の標準となる」ことは当たり前である、しかもその税金から給料。ボーナスをもらっているのだから、なおさらのことであると指摘するだろう。
しかしながら、西郷が言っていることを実行できる政治家や公務員は、明治の時代であっても現代でも、十人に一人いるかいないかである。むしろ、「家屋を飾り、衣服を文り、美妾を抱え、蓄財を謀る」ことが普通である。自分のお金ならまだしも、血税でそうさせないためには、これらの我欲があるのは普通であるという前提のもとに、この我欲が出にくいような仕組みを創る以外にないのである。
国家運営の実務は公務員が担っている。最近の汚染米事件や年金改ざん問題にしても、公務員が起こすさまざまな問題は今に始まったことではない。江戸時代にも、明治。大正・昭和・平成と役人、官僚、公務員による汚職などの問題はいつの時代にもあり、これからも連綿と続くことである。これを防ぐためには、仕組みや制度をどんどん変えていく以外にない。
国や地方のために働いているのだから身分や生活が保証されるのは当然のことであると言うかもしれないが、実際に不適格な人がいるのも事実である。定年までの終身雇用であり、民間企業のように不適格といってクビにすることは簡単にできない。
いったん公務員に採用されたら九八%以上の人は定年まで辛抱している。地位にしがみつくようになってしまう。
終身雇用の必要性がないところは十五年年期奉公制にするとか。民間企業のスピード効率を取り入れるとか。財源が税金だからできる概算要求制をなくすとか、さまざまな制度改革や仕組みを取り入れることによって、消費税率を上げなくても済むぐらいの節税になるはずである。税を徴収し使う側の人間(政治家、公務員)が権力・権限を持つことになるのであるから、西郷の言う「万民の上に位する者、己れを慎み、品行を正しくし…」となるようにするためには、何度もいうように仕組みや制度を徹底して変える以外にない。