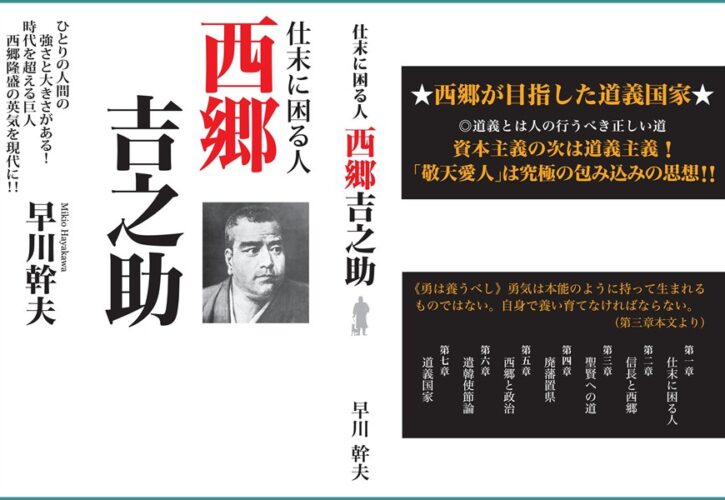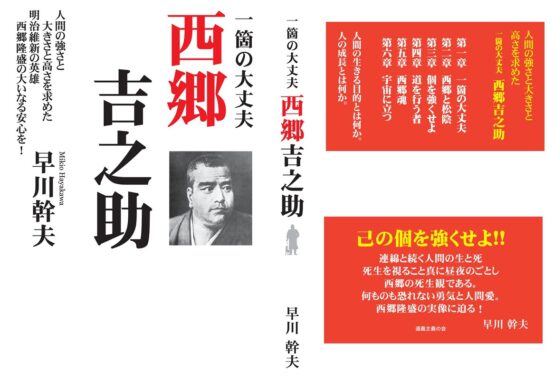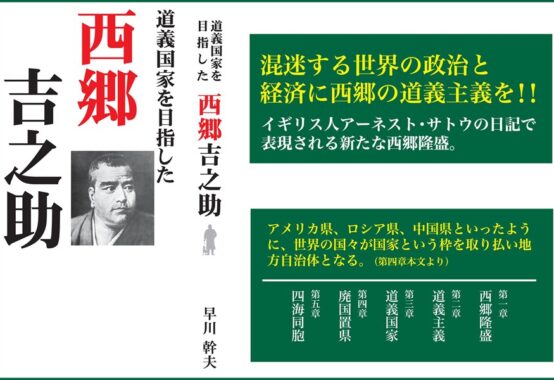第六章 這韓使節論
いまだに「征韓論」
現在でも高校生の日本史の教科書では西郷は征韓論に敗れ下野するとある。そこでは「士族は藩をつぶされ職を失い、四民平等によって苗字を名乗る特権も奪われ、徴兵令の施行によって兵士としての利用価値もなくなってしまった。そのため彼らの新政府に対する不満には凄まじいものがあった。もし百五十万人以上いる士族が一斉に蜂起したら、政府などひとたまりもない。これを西郷は恐れたのである」「政治家が国家の不満を海外へそらすというのは、昔からよくある手です。西郷は、朝鮮半島へ派遣する兵力として不平士族を用い、彼らに存分に戦ってもらってその不満を解消させようとしたのです」と説明している。
もし、本当に西郷がこのように考えていたとしたら、西郷は馬鹿者であり大した人間ではない。西郷自身でも「言動が異なっていたら西郷はつまらぬ奴だと見限ってしまってよい」と言っている。単細胞な三流政治家ではあるまいし、士族の不満をそらすという理由で征韓するはずは三百%ない。
西郷はただでさえ理解しにくい人間であるのに、このままでは永遠に「旧体制の人間」であり、「士族階級の擁護者」であり、「政策ビジョンを持ち得ない、武断主義の首魁」で終わってしまう。西郷は、西郷レベルの人間もしくは西郷と同気質の人間でなければ、その行動原理や心情は理解しがたい。西郷の行動パターンは類型がないから、歴史家でさえ自己の経験に当てはめ「人間はこういう行動をするはずがない」と思い込んでしまう。
利口な人間であれば代表参議となって表に立ち廃藩置県を断行したり、旧主島津久光の恨みを買い「西郷の罪状」をつきつけられたりはしない。大久保のように西郷の後ろに隠れ、長く大久保を重用した旧主久光の恨みを直接買ったりはしない。西郷と大久保は久光をだましだまし操縦して薩摩藩を討幕へと導いた。久光は、討幕後は島津幕府が成立すると思っていた。それで西郷と大久保にだまされたと怒った。
廃藩置県が断行されたときは、西郷に対する怒りはおさまらず自邸で花火を打ち上げ続け鬱憤をはらしたという。
実際七十七万石の大藩薩摩が討幕に舵を切ったことが明治維新につながったと言っても過言ではない。穿った見方をすれば、大久保は明治政府の中央集権化は絶対必要と考えていたであろうし、廃藩置県は避けて通れないと思っていたであろう。
同時に、それによって薩摩藩は消滅することになる。久光の激怒が想像できる。廃藩置県後四カ月足らずで、二年近くも日本を離れ洋行したのは、久光の怒りを避けほとばりをさますためであったと思われても仕方がない。日本に残った西郷は久光に「西郷の罪状十四カ条」をつきつけられ、参議・陸軍大将。近衛都督の身分で鹿児島に出向き久光に謝罪している。怒りを爆発させた久光をなだめるため、西郷は半年近くも鹿児島に滞在した。
西郷はこの後、西南戦争を起し反乱軍の大将として死んだため、自身で弁明することができず、勝者の歴史が大久保ら政府の都合のよいように形づくられていった。これは真実の大部分を物語っているはずである。「征韓論者」西郷の下野、そして士族最大の反乱西南戦争と結びつけるという型である。悪いのは西郷である。
今、征韓などすべきではないと主張する「内治優先派」という言葉までつくられ大久保らを擁護している。鹿児島は政府の命令に従わず、独立国化していた。打たれても止むを得ないという考えである。この論理で征韓論から西南戦争までがつながっていると多くの人は信じている。
次に大久保の視点で考えてみる。信長死後の秀吉がそうであるように、秀吉死後の家康がそうであるように、権力指向者は少しでも自己の権力基盤を拡充強化しようとするのは当然のことである。まず大久保の行動パターンを見てみる。薩摩をあれだけ改革できたのは斉彬が藩主という権力を得たからであり、どんなに英明といわれても世子のままでは成せなかったこと。これにより、自己の理念理想を実現するには権力を手にしなければならないと理解した。斉彬亡き後、次の権力者は久光であると狙い定め、久光を動かすことを目標としたこと。先ず久光に近づくため大久保は碁を習った。碁の相手をしてもらいながら時間をかけ少しずつ能力を認めさせた。大久保は権力者の信頼を得て、その権力と権限を借りて、自らの権力権限を行使するという手法をとった。
門閥の出身ではない下級藩士の大久保としては無理からぬ方法ではあるが、権力者久光の逆鱗に触れることは絶対に避けねばならなかった。これは西郷が久光の命令を無視し、死罪に次ぐ沖永良部島への遠島処分を受けたことを反面教師とした。大久保は自らの身の安全と用心のため、そして自分の性格も相まって西郷のように独断独行はしない人物となった。
政治手法は久光に倣い自身も厳正な統制主義者となった。 一般の組織でも上司は部下が自分より厳しい処置をすることを好む。寺田屋事件は久光が考える以上に厳しい処置を大久保が演じた例である。
討幕が現実味を帯び朝廷が権力の中心になってくると、大久保は朝廷内を切り盛りできる岩倉具視との関係を強化した。自己の権力を維持・拡大する基盤を薩摩藩の権力者久光から朝廷の権力者岩倉へ移したのである。
(三)次は権力基盤のよるところを人ではなく組織に求めた。岩倉の望みは王政の復活であり朝廷の権威の確立である。明治になってそれが果たせつつある今、岩倉を当てにすべきではないと思った。それで大久保が考えたのは、自らが立つ権力組織である。大久保が信じる富国強兵策を具現化するには、全国を統べる組織をつくりその長になることであると考えた。
以上のことを考えると、廃藩置県は西郷を利用する以外なかったと考えられる。理由は次の二点である。①薩摩藩兵と他の藩と兵への人望力・影響力は西郷を超える者はいない。②討幕に全藩を挙げて尽力した薩摩藩をつぶされた久光の怒りと恨みを考慮しなければならない。それで、郷里で隠棲生活をしていた西郷のもとへ上京の勅書を岩倉に届けさせた。
自らも同行し嫌がる西郷を説き伏せ、廃藩置県実施の代表者として引っ張り出したのである。断行後の久光の怒りを考えたとき、久光の性格を知っているだけに、洋行することも最初からシナリオに入っていたのかも知れない。久光と西郷の関係はもともとよくない。お互い嫌い合っている。そこへいくと久光土早 と大久保の関係は違う。明確な主従の関係であり、その久光に重用され権限を与えら絲れてきた。それが久光の所有する藩と領民を消滅させたとなると、裏切りであり主君への謀反となり、明智光秀のような悪名を冠せられぬともかぎらない。大久保に対する久光の怒りと恨みは、西郷に対するそれの数倍に達するに違いない。大久保はこれを回避したかったのである。